�O�c�NJy�틳���@Wind Instruments Labo�̃w�b�_�[
�O�c�NJy�틳���@Brass��Wind Instruments Labo

����ɏ���āA�����o�������Ȃ��I

���ꂾ�Ƃ���ƁA�������c�B
�g�����y�b�g�E�R�����`���X�A�����邱�ƂȂ�
���傫�����ƁA��������
���{�ł́A���܂��ɂ����郌�x���ŁA�u���̑傫�����Ƃ́A�������Ƃ��v�Ƃ����Œ�ϔO������B
����́A�Ƃ�ł��Ȃ��ԈႢ�ŁA�ނ��돬�����ق��������B
�������Ƃ����Ă��A���������������ł́A��X�������ɂȂ�B
���̈��͂����������A�\�t�g�ȉ��A�Ƃ����̂��������B
�����������́A������ƕ����ƁA�S�n���������ŁA�������Ďh���I�ł͂Ȃ��B
�Ƃ��낪�A�����}�C�N�Ɍ������Đ����ƁA���������͂ɂȂ�B
���ꂪ�A�E�B���g���E�}���T���X��E�H���X�E���[�j�[������Ă��邱�Ƃ��B
�ނ�̐������߂��Œ����ƁA�ƂĂ����炩���A�����₭�悤�ł���B
�������A�����}�C�N�ɏ��ƁA���̖��x���Ⴄ����A���̂������j��͂ށB
���̗����オ�肩�����A�Ⴄ�̂��B
���{�̃o���h�w���҂ɁA�c�O�Ȃ��炱�̂�����̗������킩���Ă���l�́A���ɂ����Ȃ��B
�ނ���A���ԓ��ɂ悭��������A�����悤�ȉ����A�����̂����B
�݂Ȃ���̎���ɂ��A���������w���ҁA�v���C���[�������̂ł͂Ȃ����B
�Z�N�V�����̒��ɁA��l�����n���ł��������o���A����̉��������Ă��܂��悤�ȃq�g�͂��Ȃ����낤���B
����������A�ЂƂ����A�������@������B
�������獡�����A�����o���̂��I�i�j
�����̃X�s�[�h
�O���Ɋ֘A���邪�A�ނ��A�t�H���e�̎w����������ł́A���E�h�ɐ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��������{�́Amp��mf�̒��Ԃ��B
�܂��A���̒���傫���J���Đ����l�����邪�A���ɃX�s�[�h�����o�Ȃ��B
�d�����A��݂Ȉ�ۂ�^����B
����ł́A���̒����������ۂ��āA�ׂ������X�^�C�����A���E�W�����B
���̂ق����A�����t���[�Y��A�㉺�̓����ɓK���Ă��邩�炾�B
���Ǝ��̂�������傫���J���Đ����l�́A�ׂ����t���[�Y�������Ȃ��B
���͂�A�N�����b�p���炢�����A��ڂ��Ȃ���������Ȃ��B
������A�����Ɍ������Ⴄ�Ɓc�A
���[�A����[�J�b�R���`���I�i���j
����Ȃ��Ɩ{�l�ɂ͌����ɂ����Ƃ����l�́A
�������A�����o�������Ȃ��̂����I�i�Ĕ��j
�����邳���o���h
���邳�����R�ɂ́A����������B
�����ɁA�Q�_�B
�@�S���̐��������Ԉ���Ă��āi�܂�͂�ł��āj�A�S�̂��A������ԂɂȂ�B
����́A���̃v���C���[�̉����傫�����A�����Ď��������������Ă��܂��ꍇ���A����B
���Ă��āA���ꂪ����ɔg�y����B
�A�r�b�O�o���h�Ȃǂɑ������A�M�^�[��x�[�X�A�L�[�{�[�h�̓A���v��ʂ��ĉ����g�債�Ă���̂ɁA�NJy��ɂ͂܂������}�C�N���Ȃ��B
�NJy����ł����̂�������A�x�[�X��M�^�[�̉��ʂ��A�A���v���x�����ŏ����ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����́A�����W�̐ӔC�ł�����B
���������Ŋׂ肪���Ȃ̂́A�u����A����̉��͏������̂��ȁv�ƕs���ɂȂ邱�Ƃ��B
�t�ł���B
�������Ȃ��ق����A�������̂��B
���̊��ŋq�Ȃɕ�������NJy��́A�ԈႢ�Ȃ��A�I�[�o�[�u���E���Ă���B
���n�C�E�m�[�g�̕s�v�c
���NJy��Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ŁA�n�B�����l�̉��قǁA�����I�ł͂Ȃ��Ȃ�B
�S�n�悭�A���炩�������ɂȂ�B�����ƕ����Ă�����B
�����ۂ��A�Z�p�̂Ȃ��l�قǁA���܂ł��p���p���Ƃ����������̗v�f�������Ȃ��B
������A�u���L���C�����悤�ȉ��ł���B
����ƁA�ǂ��������Ƃ��N���邩�B
�N���[�N�E�e���[�̃n�C�f�����A���[�E���[�K���̃n�C�c�̂ق����A�����������Ă��܂��I
�Ƃ��ɁA�f�l���������i�f�l�Ƃ����\���͂��܂�悭�Ȃ����j�B
���ꂪ�A�u�n�C�E�m�[�g�̕s�v�c�v�ł���B
���̌�A���[�E���[�K���͂Q�T���߂��ĉ����o�Ȃ��Ȃ�A�N���[�N�E�e���[�͂W�O���߂��Ă��������y�₩�ɑ������B
���́A���y�I�ɂ͂̓��[�E���[�K���̂ق����D�݂����A���t�Z�p�𓐂݂����̂́A�e���[�ł���B
�R�R�ň��l�ɎˎE���ꂽ���[�K���́A���łɉ����o�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA���y�ƂƂ��Ă͂���Ӗ��A�K����������������Ȃ��B
�����Ẵz�[���Z�N�V�����̈Ⴂ
�ȉ��ɁA�A�����J�̈ꗬ�I�[�P�X�g���ƁA���{�̃g�����y�b�g�Z�N�V�����̉��̏o�����A�}�������Ă݂��B
�@�́A���̉��ɐc������A���������Ă���B���ćA�́A�肫��Ńv���X���Đ����Ă���̂ŁA�S�̂����邳���B
���ꂪ�A�����A���{�̃o���h���Ɋ����Ȃ��Ƃ��闝�R�ł���B
�h�g�b�v�h�ƌ����郌�x���ł��A���l�ł���B
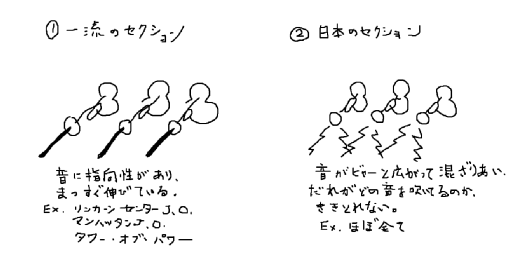
���ق�����c��܂�
���܂ɁA�ق�����c��܂��Đ����l������B
�������A�{�l������Ŗ����Ȃ�A���̐l�̎��R�ł���B
�������A����͂��̐l�́A�P�Ȃ�Ȃł��邱�Ƃ������B
�܂��A�������ɉ��A�֊s�̂ڂ₯���A�d�����ȉ��ł����Ȃ��B
�u�����͖j��c��܂����ƂŁA�����ӂ��悩�ɂ��Ă���̂��v
�Ǝ咣����l���A���邩������Ȃ��B
����Ȃ�A�ق�����c��܂����A�}�E�X�s�[�X��傫���������������B
�Ȃ��A�f�B�W�[�E�K���X�s�[�̉����d�����Ȃ炸�A�X�s�[�h������̂́A���|�I�ȑ��ƁA���̈��͂����邩��ŁA���ϓI�ȑ̊i�̓��{�l���A�^������ׂ��ł͂Ȃ��B
�����I�ɁA�����ċ@�\�I�ɉ��t����ɂ́A���̒��͂˂ɋ����ۂׂ��ł���B
����̂悤�Ɂu�X�s�[�h�v���d������鎞��ɂ����ẮA�Ȃ����炾�B
���뜜�����X��
�����̊w���̒�����t��ł́A���y�����łȂ��A�u�_���X�v����I����悤���B
����́A�����ւ�뜜�����X�����B
�������ł��Ă��Ȃ��i�K�ŁA�����������ׂėx������̂����肵�Ă���B
�܂�łǂ����̍��́A�q�������̂悤���B
�w�����x���ŁA�W�q��ړI�ɂ���ׂ��ł͂Ȃ��B
�^���ɉ��y�����Ɏ��g�ނׂ����B
�{�l�����������I�ɂ���Ă���Ȃ�܂��������A����������A���t���w�����Ă�点�Ă���Ƃ���ƁA���ꓹ�f�ł���B
���ɂ́A�x�邱�Ƃɖ{�ӂł͂Ȃ����k�����邾�낤����A�C�̓łł���B
���������l�́A���ЁA�������͂ɕ������A�u���͂��ǂ�܂���v�ƁA�錾���Ăق����B
���������Ċς�
�S���ŁA���ꖳ���̃R���T�[�g�������Ă���B
�����ɂ́A�����ʂƈ����ʂ�����B
�����������̂����ɐڂ��Ă���ƁA�����u����Ȃ��̂��v�ƂƂ炦�Ă��܂��B
�n���s�s�ł������y�≉�t�ɐڂ���@��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ����A���ԂƂ����̗]�T�̂�����́A���ЁA�u�u���[�m�[�g�����v��u�T���g���[�z�[���v�ȂǂŁA�{��̉��ɐG��Ăق����B
�����āA�ł��邾�����ߋ����ŁA�������ǂ�Ȃӂ��ȃ^�b�`�ŁA���ʂŏo�Ă��邩���A�m�F���Ă��炢�����B
�����炭�A������邾�낤�B
���������ꂪ�A����I�Ȑi���̂��������ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B
�������ꗿ�́A���ꑊ���̉��Ɖ��y�ʼn����Ă����B
���ǂȂ�Ƃ��炾��
�e���r�ł悭�A���t�y���̎w���҂����k���ǂȂ���A���k�͗܂𗬂��A�������Ɂu�I�[�f�B�V�����v�Ɖ]�����̑I�������ŁA���i���Ă͊�сA�����Ă͔߂��݁A���Ă���̂����������B
����́A�����ւ�A���������B
�ǂȂ�����A�������肵�Ă���w���҂́A�����̊NJy��ɑ��閳�����E���\�͂�������ɉ����Ă���̂ł����āA�����Č����́A���k���ɂ���̂ł͂Ȃ��B
���k�́A��B�̑��x�Ɍl���͂����Ă��A�K�ȁu�d�g�݁v���w�ׂA����ł����܂��Ȃ�B
����A�\���̕�ɂł���B
�l���Ă݂Ăق����B
���̐搶���A���܂��y����A���Ȃ��̑O�Ő����Č��������Ƃ����邾�낤���B
�����Ȃ��̂ł���A�����Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B
�����͐����Ȃ��̂ɁA���k�ɑ��ē{��Ƃ����̂́A������k�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B
����ȕ�������́A�������Ƒ���ׂ����B
�Ȃ��A�y�����搶�Ȃ�A�����Ă��������낤�B
�����z�^�̈��
�ȉ��̉f���́A�����J�[���Z���^�[�E�W���Y�E�I�[�P�X�g���ł���B
�g�����y�b�g�́A��O����A�}�[�J�X�E�v�����^�b�v�A�P�j�[�E�����v�g���A���C�A���E�J�C�U�[�B
���ɍ���̂��A�E�B���g���E�}���T���X�ł���B
�r���łR�l�̃o�g�����W�J����邪�A�����������ł��邱�Ƃ��킩��Ǝv���B
�����āA�n�C�m�[�g�����ʂłȂ��A�X�s�[�h�i�^�ɏW�߂��A�ׂ����j�ł��邱�Ƃ��B
�ƂĂ��A�Â��ł���B
https://youtu.be/CL0HgC1jbNI
�����K�̌���
���̓����K���J�n���āA30���o���āA�]�v�ɐO���d���Ȃ�i�U�����Ȃ��Ȃ�j�悤�ł́A���̃A�b�v�@�͊Ԉ���Ă���B
���������K������A10������30����A30������1���Ԍ�A�Ƃ����悤�ɁA�ǂ�ǂ̏o���X���[�X�ɂȂ�B
�����Ȃ��Ă͂��߂āA�t���[�Y�╈�ʂɎ��|����ׂ��Ȃ̂����A�w���ł͑����̏ꍇ�A�����o�Â炭�Ȃ�������ɁA�S�̗��K���n�܂�B
���̂��߁A���t�̑��ɂ̓X�g���X�����܂�A���t���鑤�ɂ͋��|�����~�ς���B
���z�ł���B
������J��Ԃ��ɂȂ邪�A���K���Ԃ����������ƂɁA�����́u�B�����v���o���A����ł������A�ƂȂ�₷���B
�����I�ȗ��K�ɂ����ẮA�l��1���ԁA�S�̗��K2���ԁB
���ꂭ�炢�ŏ[�����낤�B
���Ƃ́A�V�ԂȂ�A����ɍs���Ȃ肷������B
�Ԉ���������ɂ����玞�Ԃ������Ă��A�O�͏��߂邵�A�������͑������A�����Ȃ�Ǝ����́u�v���C�h�v����邽�߁A�l�Ԃ͑��l�̈������]���͂��߂�B
���������������@�ŏ�B���������������A�����Ă����Ă����̐l�͗��K�𑱂���B�Ȃ��Ȃ�A�y�������炾�B
�����āA���Ԃ������^�����n�߂�B
10���́A���̃��j���[�A����10���͂���A�Ō��10���A�͂��A�ł�������A���āA�n�߂܂��傤���Ƃ��������ł���B